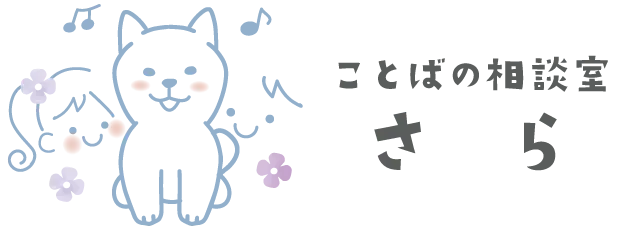R3つの映像を見せていただきました。
映像を観る
→ 近くの方と感想をシェアする
→講師の先生のお話
といった形で進行していきました。
VRの映像を観るのは初めてでした。
認知症には誰がなってもおかしくなのですが、
実際に装置をお借りしてつけてみると、
目の前に見えてくるものが次々と「あれ?」と思い、どんどん混乱して不安が大きくなっていきました。
今回のプログラムを企画されている会社では、発達障害の感覚過敏についてのワークショップもメニューにあるとのことでした。
いろいろ質問させていただきました。
実際に体験し共感することが難しいものであっても、
お子さんの感覚の鋭敏さを体験。
実際にどのくらい苦しかったり、痛かったりするのか、
怖いですが、ざっくり「大変だ」ですまさずに、
そのためにもこれは一度VR体験しておかなくちゃと思いました。
予算などを伺いましたが、さらだけでは難しいのですが、いくつかの団体が一緒に勉強会を企画するとここともあるようです。
ぜひ実現したいと思いました。
認知症や失語症、高次脳機能障害について、病院勤務時代にお世話になった、久ぶりにたくさんの患者さん、ご家族さんたちのお顔が浮かびました。
その中でVR体験のビデオにあったように「大丈夫ですよ」と安易に声をかけてしまっていたことを反省しちゃいました。
このようなケースでは、どうかかわったらよいか?について、会場の皆さんの感想のシェアも大変刺激を受けたり、勉強になりました。今後の接し方、考え方に生かしていきたいと思います。